-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
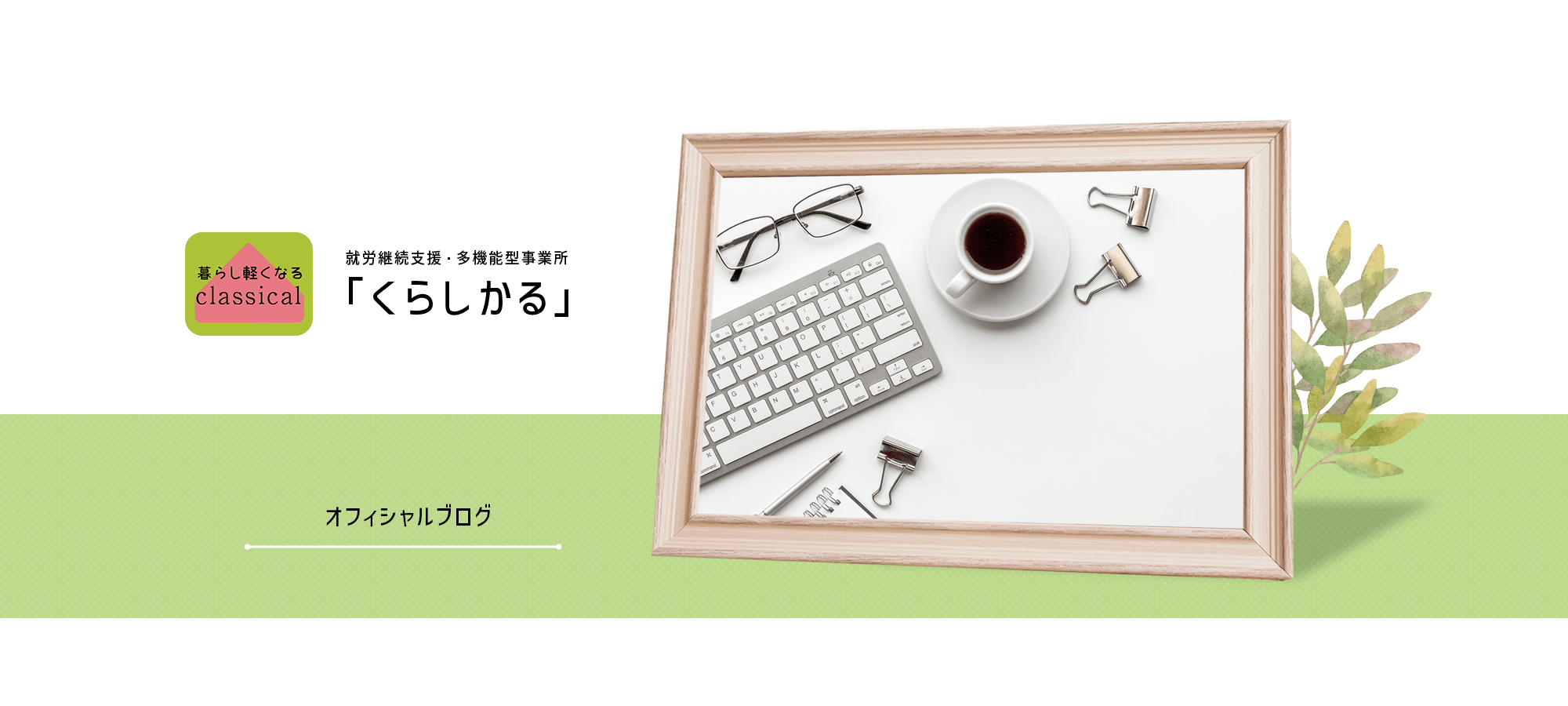
皆さんこんにちは!
株式会社RELIFE、更新担当の中西です。
さて今回は
~社会参画~
「就労支援」と聞くと、多くの人は職業紹介や職業訓練を思い浮かべます。しかし、長期無業者やひきこもり、高齢・障害などによって社会との接点が失われている人々にとっては、いきなり働くことは高すぎるハードルです。
そこで近年注目されているのが、「社会参画支援」というアプローチです。これは、就労の前段階である「社会との接点をつくる」支援であり、孤立や不安からの回復、自己肯定感の再構築を目的としています。
目次
社会参画支援とは、以下のような活動を通じて、就労困難者の社会的つながりを再構築する支援です
コミュニティ活動(地域イベント、農業ボランティア等)
グループワーク(自己表現、話し合い、ゲーム)
居場所支援(サロン、カフェ、フリースペース)
学び直し(読み書き、ICT、生活技術など)
アート・スポーツ・表現活動
つまり「働くことの前に、“居場所”と“役割”を取り戻す」ことを目的とした非就労型の支援です。
長期無業状態にある若年層(例:NEET・ひきこもり)
精神疾患の既往歴がある人
障害者(特に発達障害や軽度知的障害)
生活保護受給者や生活困窮者
高齢の再就労希望者
外国人、DV被害者、ひとり親など社会的孤立者
これらの人々は、自己効力感や対人スキルが低下しており、いきなり職場に入ることが困難な場合が多いため、まず「安心して通える場」と「承認される経験」が必要です。
生活困窮者自立支援制度内の「就労準備支援事業」
地域若者サポートステーション(サポステ)
障害福祉サービス(生活訓練、自立訓練、地域活動支援センター)
フリースクール、子ども食堂、若者居場所事業
ソーシャルファーム(社会的企業)
地域通貨、まちづくり活動、ボランティアセンターとの連携
これらは「労働市場」ではなく「地域社会」を舞台に、誰もが「役に立てる」「つながれる」体験を積むことが可能な場です。
関係形成を急がない:支援者が“構いすぎ”ず、信頼関係をゆっくり築く
小さな成功体験の積み重ね:ゴミ拾いや植物の水やりなど、シンプルな役割から始める
強制しない・選ばせる:活動の選択肢があり、本人の「やってみたい」に基づく
他者からの承認:感謝や褒め言葉が自己肯定感を育てる鍵
社会参画支援は「ゴール」ではなく、「就労支援へ向かう橋」の役割を持ちます。ここで得た
通所習慣
集団適応スキル
自己表現の機会
社会資源へのアクセス
は、最終的に就労移行支援、職業訓練、実習参加へのきっかけとなります。
就労支援の中で社会参画支援を位置づけることは、「働ける人だけを支援する」制度から、「誰もが少しずつ前に進める」社会へと移行する鍵です。孤立していた人が少しずつ外に出て、自分の言葉で語れるようになる――それこそが、真の自立への第一歩です。
支援者、制度設計者、地域コミュニティそれぞれが役割を果たし、誰も取り残されない支援の仕組みを作ることが、これからの就労支援の未来です。
![]()