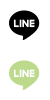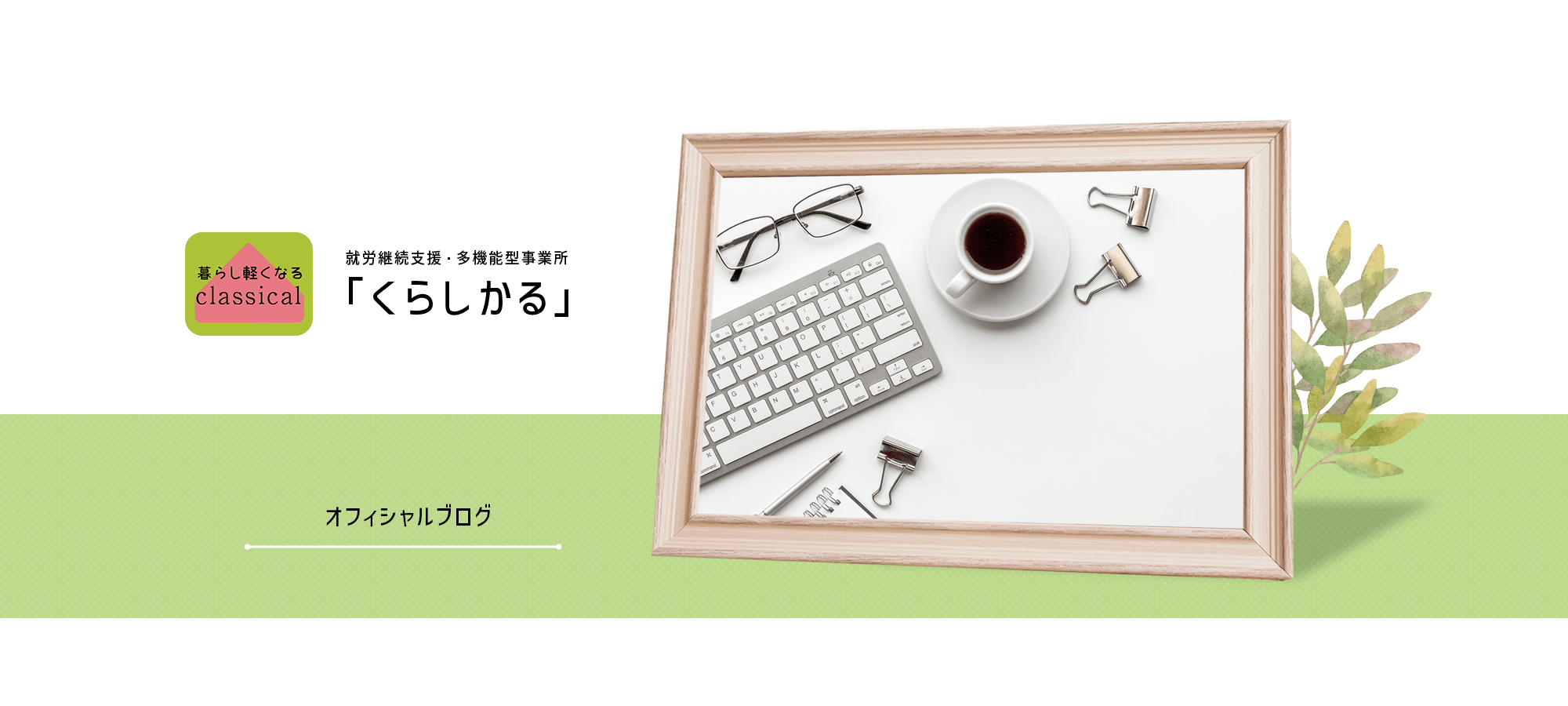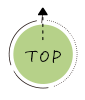就労支援の現場には、いろいろな“誤解”もあります。
「働けない人を働かせる仕事」
「甘やかす支援」
「根性をつけさせる場」
どれも違います。
就労支援は、本人の力を引き出し、環境を整え、企業と社会に橋を架ける仕事です。本人だけを変えるのではなく、働く環境側にも働きかける。だから就労支援の成果は、本人・企業・支援者がチームになったときに最大化します🤝✨
第2回では、就労支援の魅力を「企業との関係」「支援の戦略性」「チーム支援」「支援の未来」という視点で深掘りします😊
目次
1)就労支援は“企業支援”でもある。働く場を整える仕事🏢🛠️
就労支援の本質は、本人の努力だけに頼らないことです。
なぜなら、働き続けられるかどうかは、本人の特性と職場環境の相性で決まる部分が大きいからです。
-
作業手順が曖昧だと混乱する人
-
音や匂いに敏感な人
-
いきなり人間関係が濃い職場だと消耗する人
-
指示が一度に多いとパンクする人
-
休憩の取り方が分からない人
こうした特性を「本人の問題」として終わらせず、企業側に環境調整を提案する。これが就労支援の重要な役割です。
例えば、
-
指示を紙やチャットで見える化する
-
作業を細分化して順番を固定する
-
相談窓口を決める
-
勤務時間を段階的に伸ばす
-
配置転換や担当変更を検討する
こうした調整で、働きやすさは劇的に変わります。
就労支援は、企業にとっても「人を活かすためのパートナー」になれる仕事です🏢✨
2)支援は“気持ち”だけじゃない。段階設計と戦略がある📋📈
就労支援は優しさだけで成立しません。
成果を出すには、支援の段階設計が必要です。
-
生活リズムの安定
-
通所・作業習慣
-
基本的なコミュニケーション
-
スキル訓練(PC、軽作業、接客など)
-
職場体験(実習)
-
就職活動(応募、面接)
-
定着支援(相談、調整)
このステップを、本人の状態に合わせて組み替え、無理なく進める。
焦らせず、停滞させず、崩れたら戻って立て直す。
この調整力が、就労支援のプロの腕です🤝✨
支援計画は、言い換えれば“成功確率を上げる設計図”。
支援者は、本人のペースを尊重しながらも、未来に繋がる道筋を作ります📋✨
3)「できない」を責めない。「できる条件」を一緒に探す🔍🌈
就労支援の現場で大切なのは、本人を評価することではなく、本人が力を発揮できる条件を探すことです。
-
どの時間帯なら動ける?
-
どの作業なら集中できる?
-
どんな声かけなら受け取りやすい?
-
どのくらいの休憩が必要?
-
どんな環境なら疲れにくい?
支援者は、本人の「できない」を叱るのではなく、
「できる条件」を探し、整え、試し、積み上げます。
この考え方は、本人の自己肯定感を守ります。
「自分はダメだ」ではなく、
「条件が合えばできる」
という感覚が育つと、挑戦が続きます😊✨
就労支援は、本人の未来を“可能性”として扱う仕事です🌱✨
4)チーム支援が力になる。家族・医療・行政と連携する🤝🏥🏢
就労支援の現場では、支援者だけで抱えません。
家族、医療(主治医・カウンセラー)、行政、学校、企業…。関係者が多いほど、支援は強くなります。
-
体調悪化の兆候を早めに共有する
-
服薬や通院の状況を踏まえて負荷を調整する
-
生活面の支援と就労面の支援をつなぐ
-
家族への説明と安心づくり
-
企業へのフォローと調整
こうした連携は手間がかかります。でも、その手間があるからこそ、本人は一人で抱え込まずに済みます。
支援の本質は、「支える人を増やすこと」でもあります🤝✨
5)支援が生む“連鎖”。一人の就職が次の誰かの希望になる🌱✨
就労支援の現場では、誰かの成功が次の誰かの希望になります。
-
就職した人が近況報告に来る
-
その姿を見て「自分もいけるかも」と思う
-
先輩利用者が後輩の相談に乗る
-
支援の場に前向きな空気が生まれる
就労支援には、こういう“希望の連鎖”が生まれやすい。
支援者は、その連鎖を育てる役割も担っています😊✨
第2回まとめ|就労支援は「本人と企業と社会」をつなぐ架け橋🌈🤝✨
就労支援の魅力は、
-
企業側にも働きかけ、環境を整えられる🏢
-
段階設計と調整で成功確率を上げる📋
-
「できる条件」を探して可能性を育てる🔍
-
チーム連携で支援を強くできる🤝
-
成功が希望の連鎖を生む🌱
就労支援の仕事は、人の人生を変える力があります。
でもそれは、無理やり変えるのではなく、本人が自分の力で前に進めるように支える力。
「支援があるから働ける」を当たり前にする、価値の大きい仕事です😊✨