-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
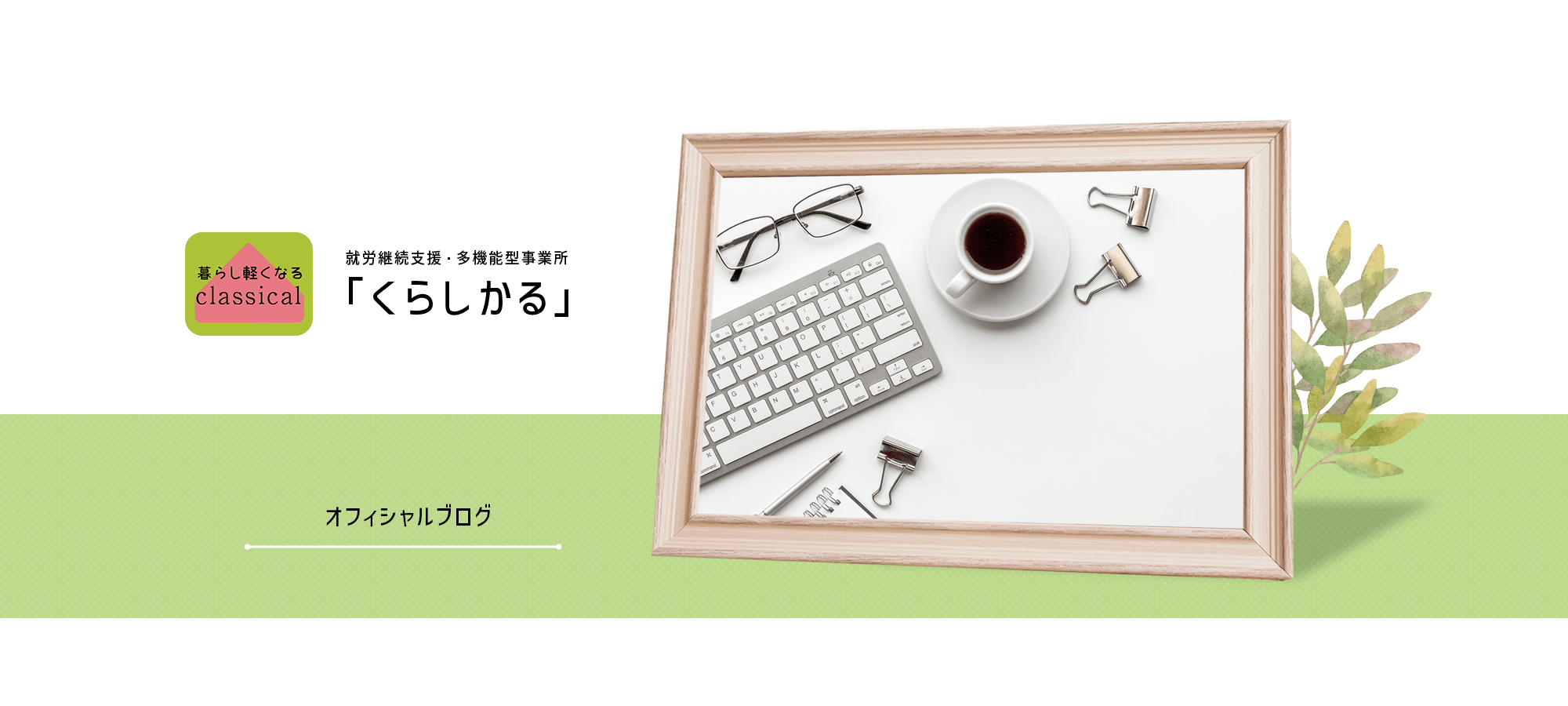
皆さんこんにちは!
株式会社RELIFE、更新担当の中西です。
さて今回は
~法改正に伴って~
目次
就労支援事業とは、障害や病気、さまざまな事情で一般就労が難しい方に対して、働く機会や訓練、サポートを提供する制度です。
就労移行支援:一般企業での就職を目指すトレーニング
就労継続支援A型・B型:雇用契約を結んで働く形や、作業訓練を中心とする形
生活訓練・自立支援:働く以前に生活のリズムやスキルを身につけるサポート
これらの事業は「障害者総合支援法」に基づいて運営されており、時代に応じて法改正が行われてきました。
それまでバラバラだった福祉制度を一本化
就労支援事業が法律に明確に位置づけられる
対象が「障害者」から「難病患者」にも拡大
就労支援事業所における人員配置・運営基準が整備
「生産活動収入」や「利用者の工賃向上」を重視
就労定着支援が新たに創設され、企業就職後のアフターフォローが制度化
A型事業所における「雇用契約の適正化」
B型事業所での「工賃向上計画」の義務化
ICT活用による事務の効率化や在宅就労の導入検討
2024年には「報酬改定」で、就労定着率や工賃水準に応じた評価が強化
透明性の向上
法改正により、事業所運営の基準が明確化され、不適切な運営を防止できる。
利用者本位のサービス強化
単なる作業提供から、就職・定着を見据えた支援へシフト。
事業所の経営課題
報酬改定によって「工賃向上」「就労実績」が重視されるため、事業所には成果を出す工夫が求められる。
人材育成の必要性
専門性を持ったスタッフが求められるようになり、研修・教育制度が拡充。
これからの法改正の方向性としては、以下が予想されます。
デジタル活用:テレワークや在宅就労支援の制度化
多様な働き方への対応:副業や短時間労働など柔軟な支援
地域共生社会の推進:企業・自治体・地域が連携した就労支援モデル
成果報酬型制度の強化:支援の「量」より「質」と「成果」を重視
就労支援事業における法改正は、単なる制度の見直しではなく、利用者の自立支援と社会参加を推進する大きな仕組み です。
そのたびに現場には新しい課題が生まれますが、同時に利用者の選択肢や可能性も広がっています。
オーダーメイドのように一人ひとりに合った支援が求められる現代。
法改正を追い風として、就労支援事業は今後ますます社会に不可欠な役割を担っていくでしょう👥🌍✨
![]()